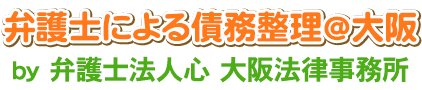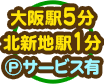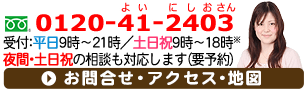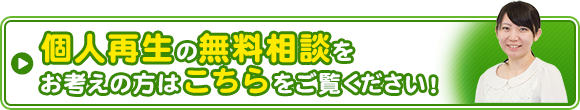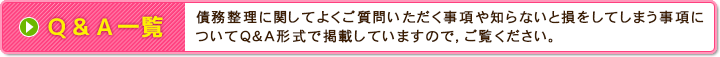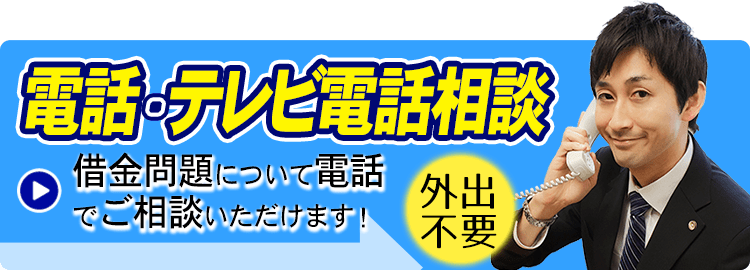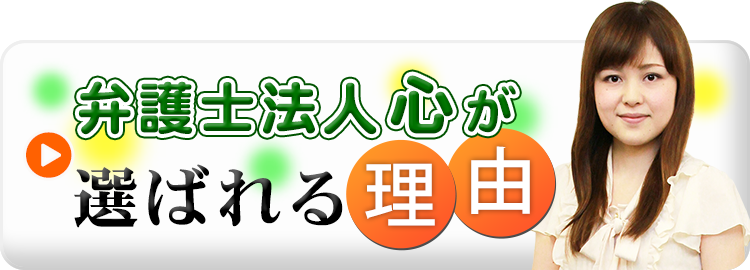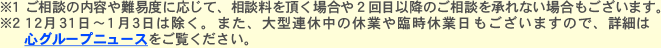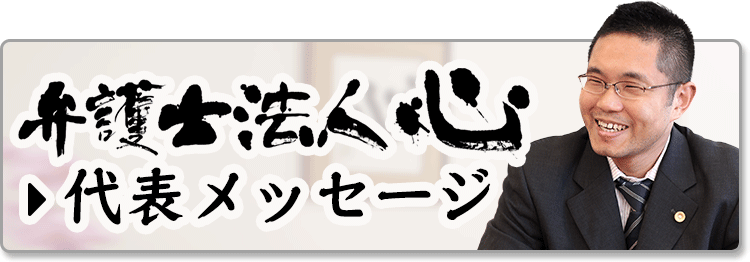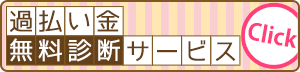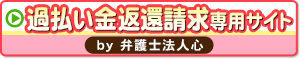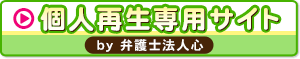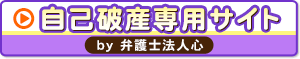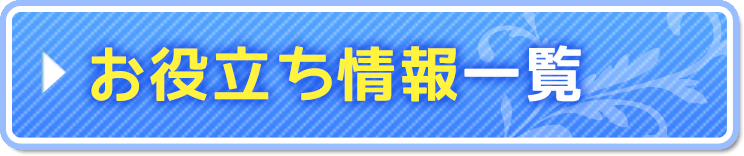「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生で減額されない債権
1 共益債権、一般優先債権、非減免債権について
個人再生は、債権額を減額して分割で支払っていく制度として紹介されます。
ただし、注意が必要なことがあります。
それは、どんな債権でも減額してもらえるというわけではないことです。
債権の種類・性格によっては、個人再生の減額の対象とならないものもあります。
民事再生法では、このような個人再生でも減額されない債権について、共益債権、一般優先債権、非減免債権の三種類に分類して定めを置いています。
2 共益債権について
まず、共益債権は、民事再生法121条で「共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」「共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。」と書かれていますので、再生手続きによる減額の対象にならないですし、その他の金融債権者の債権よりも優先して支払わないといけません。
この共益債権とはどういうものかというと、「共益」という言葉からも分かるように、その債権の発生した経緯が、個人再生手続きの関係者全体の利益につながっているような債権のことです。
具体的には、民事再生法119条1項1号以下に「再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権」などが挙げられています。
3 一般の優先債権
次に、民事再生法122条では一般の先取特権その他一般の優先権がある債権については、「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」とされています。
この優先債権の関係では、国税徴収法8条に「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。」とされていることにも留意する必要があります。
この規定から、税金については、個人再生の減額の対象とならず、随時弁済しないといけなくなることがわかります。
4 非減免債権
最後に、民事再生法229条2項では、再生計画の債務減免の影響が及ばない権利について列挙しています。
具体的には、① 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 ② 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) ③ 次に掲げる義務に係る請求権(イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務、ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務、ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務、ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務、ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの)とされています。
このように、損害賠償債務や養育費のような家族関係の義務にもとづく支払いについては減免の対象外とされているものがあるため注意して確認する必要があります。